着物や浴衣は和服の一環です。
つい和服と聞くと着物を想像してしまいます。
イベント時を少し思い出してください。
男性は羽織袴を着たり、大学生は卒業式に袴を穿いたりします。ワンピース長着を着物とすれば、これらは着物といえませんが和服です。
この記事では着物と和服の意味と違いを説明します。
洋服との関わりからみた着物と和服の意味と違い
着物と和服の意味と違いを知るには、着物と和服の意味を知る必要があります。
辞書ではよく和服から説明しますが、ここでは着物から。
着物と和服の意味
着物とは
着物とはワンピース長着のことです。
これを日本語で着物というだけの話で、着物は何も日本に限ったものではありません。
和服とは
和服は着物だけでなく、ツーピースの組み合わせもふくみます。羽織や袴なども和服です。
だいたい1900年ころに和服の代表が着物になりました。
この後も、学校の制服では「女学生に袴を穿かせろ」とか「着物にさせろ」とか、はたまた「洋服でええやろ」とか、議論が耐えませんでした。
私服はともかく制服は教育とのかかわりが強いので、どこの国でも論争が尽きませんね。
「和服」の曖昧さ
このように考えると「和服」とは何か分からなくなります。
辞書では日本在来のという説明が多いのですが、この理由なら「日本服」でよかったはず。
また、世界在来の服は「世服」とでもいうのでしょうか。
ファッションの世界では「日本」のような国を示す言葉には要注意。
日本古来といえば中国服の影響を無視できませんし(辞書では無視して説明していますが)、近代以降の日本人の服となると洋服になります。
つまりファッション歴史では「日本」や「和」が成立しない問題があります。
着物と和服の違い
三省堂『例解新国語辞典』
まずは中学生むけの辞典から。
着物
①身につけてからだをおおうもの。②洋服に対して、和服。林四郎監修、篠崎晃一編修代表、相澤正夫・大島資生編著『例解新国語辞典』第十版、三省堂、2021年、286頁
着物とは着る物であり、また洋服と違う衣服と述べています。
和服
つぎに「和服」をみてみましょう。
日本風の衣服。きもの。林四郎監修、篠崎晃一編修代表、相澤正夫・大島資生編著『例解新国語辞典』第十版、三省堂、2021年、1317頁
和服が日本風の衣服なのですから「和」=「日本」の等式にもとづいています。
また和服を着物と説明。先にみた「着物」は和服と説明していました。
なお、和服の対語に洋服をあげています。
かなり単純に「着物=和服|洋服」の数式が出てきます。
面白いのが次に紹介する2冊の服飾辞典です。
専門的なはずの辞典が中学生むけ辞典を超えていないことがわかります。
文化出版局編『服飾辞典』の和服と着物
どうして「和服」の意味が曖昧なのでしょうか。
文化出版局の辞典は「和服」を次のように説明しています。
明治時代に西洋の服が輸入され、洋服とよぶようになったが、これに対して従来の日本の衣服を和服とよぶようになった。文化出版局編『服飾辞典』文化出版局、1979年、979頁
和服の意味が曖昧なのは洋服から説明しているからです。
洋服があってこそ和服があるわけです。
それでは着物の説明はどうでしょうか。
普通は、着物という語を和服と同義語として用いている。現在の和服の形態の源流は、室町時代の小袖帯に始まる。文化出版局編『服飾辞典』文化出版局、1979年、979頁
普通かどうかはともかく、この辞典は着物を和服と同義だと考えています。
この辞典では現代和服の「形態の源流」として「小袖」に触れた直後に「小袖帯」の話にズレています。
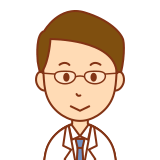
こういう叙述のズレはファッション歴史の本によくあることです。書いているテーマが同じ文章でズレる。服飾史研究者に多い「頭脳の脱臼」です。
それでは「着物」の項目をみてみましょう。
衣服。着る物がつまって着物となったのであろう。近世以降、<きぬ><ころも>に代わって用いられるようになった。(中略)今日では、身体に着るものの意味として一般に用いられ、とくに洋服に対して和服をさす。文化出版局編『服飾辞典』文化出版局、1979年、201頁
着物を衣服と述べたのが実に正解。
近世に新井白石が「衣服」に「きもの」と読みをつけたエピソードを入れながら、今日の着る物へ話を進めています。
辞書にしては自然で正直な叙述。
ただし、最後のところで洋服の対語として和服をもちだして、その代表アイテムを着物としている点には二分法の柵(しがらみが)…。
『新・田中千代服飾事典』の和服と着物
『田中千代服飾事典』の説明はどうでしょうか。
わふく【和服】〈日本の衣服〉という意味で、和服とは欧米の洋服に対するもの。とくに国際服ともいうべき洋服に対し、日本在来の衣服のこと(攻略)。田中千代編『新・田中千代服飾事典』新訂版、同文書院、1991年、1162頁
この辞典でも洋服をもとに和服を説明しています。
国際服の洋服にたいし日本在来の和服を対比しています。
着物はどうでしょう。
- 長着(通常着物とよばれる)
- 長着は和服の一番中心になるものであるところから、単に和服とよんで長着をさす
着物という長着が和服の中心なので、和服といえば長着(着物)をさすと述べています。
後の小袖が奈良時代から下着に使われていて中世・近世にアウターウェアとなったと続く説明は通説どおり。
また「着物」の項目では次のように説明しています。
着るもののことで、衣服という意味にも用いられるが、通常洋服に対し、日本の衣服、つまり和服のことをいい、とくに和服のなかでも長着をさすことが多い。田中千代編『新・田中千代服飾事典』新訂版、同文書院、1991年、235頁
着物を着る物よりも和服として説明したいようです。
「和服」の説明と同じく洋服との対語で「着物」を理解しています。
着物と和服の意味と違い
着物と和服の意味と違いを紹介しました。
着物はワンピース長着のことで和服の一種でした。
また、着物も和服も洋服と対比的に考えられることがわかりました。
洋服の導入は19世紀中期からなので、それまで日本で着用されていた衣装をすべて「和服」に一括したこともわかりました。
そして、和服は着物のようなワンピース長着だけでなく、ツーピースもふくみました。
こう考えてくると、逆に「洋服」とは何かよく分かりませんよね…。
洋和という単純な二分法で日本のファッション歴史を考えるべきではありません。
19世紀までの和服(前近代和服)はいまの着物と違って、とても多様性にとんだものでした。見ているだけでも躍動感があり、想像を膨らませてくれます。
次の記事で前近代和服の自由な着方や多様性を楽しんでください。



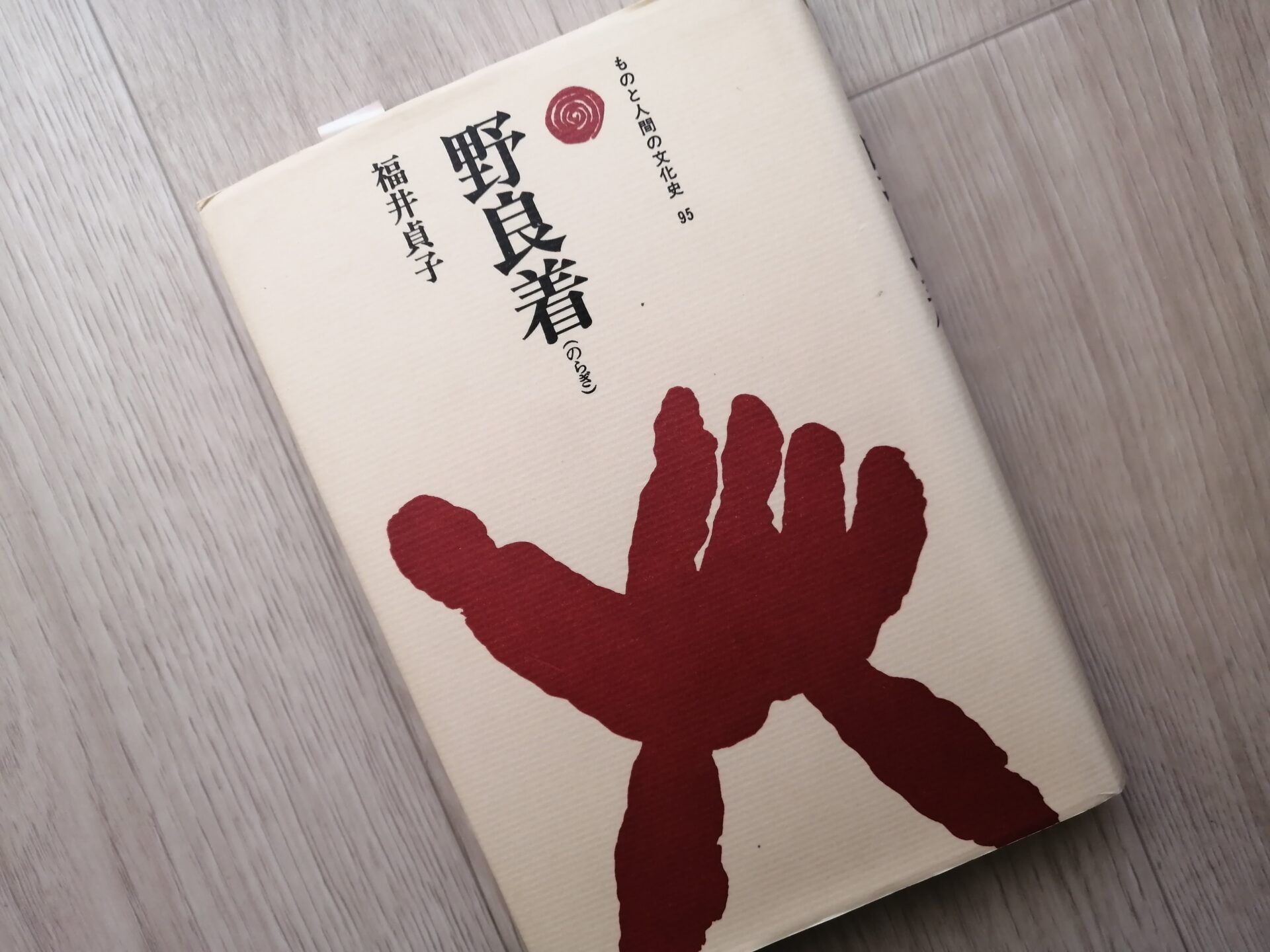
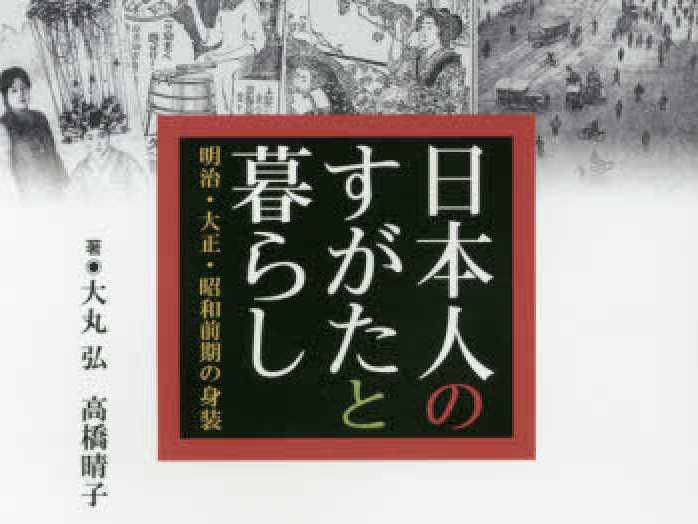
コメント