この記事ではニュー・キモノの特徴と歴史について、構成要素と経済からふりかえっています。
ニュー・キモノの特徴
表記上「ニューキモノ」とも「ニュー着物」とも。あまり「ニュー和服」とはいいません。
ニュー・キモノとは、斬新な発想を自認する人びとが制作した現代和服の総称です。
実際にどの程度まで斬新なのかは個別作品や時代傾向をみないと何ともいえません。また、ニュー・キモノはフォーマル着物に対する対語的な意味をもつので、厳密に定義があるわけではありません。
いちおう、衣服の構成要素からみるとニュー・キモノを次のように位置づけられます。
ニュー・キモノの構成要素
着物がワンピースを前提にしているのにたいし、ニュー・キモノはワンピースもツーピースも許容します。
ニュー・キモノが着物として認識されるのは、着物の普遍要素・不変要素の4点をもっているからです。
- 袂のある広袖
- 平肩の袖(連袖)
- 打ち合わせの裾
- 帯
このページのトップ写真のように、アウターの内側に帯を締めるとニュー・キモノなのかどうか、判断が難しいところ。
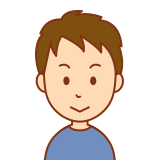
この写真の上衣は着物の構成要素をふまえているので、私はニュー・キモノとも着物とも判断します。着ているのも確かですし。
ニュー・キモノの20世紀経済
ニュー・キモノが商品の根拠とする点は、だいたい既製服で安価であること。
20世紀をとおして、極端にフォーマル化された着物とは異なる商品戦略に、ニュー・キモノは成立していました。といっても、暴利をさらっていった業者も多くありましたが。
ニュー・キモノはアンチ・フォーマルに基づくため、素材の自由度も広がり、絹にかぎらずウール、綿、合成繊維のポリエステルなども積極的に使われています。
したがって、ニュー・キモノは若年層へも断続的に流行してきました。
いまでも若年層が着物のデザインやコーディネートで新しい試みにチャレンジしています。
ただ、この新しさが時に着物警察の被害にあうことも。被害者の多くは若い着物女子です。
着物警察
2010年代から、街中で着物や和服を着た人をトイレに連れ込んで我流に着なおさせる犯罪が都市部で見られます。
いわゆる着物警察です。
着物警察は錯覚や先入観を強くもっています。
- 記事は絹
- 足袋は白色
- 帯の締め方は自分の習った方法
着物警察にはシニア脳筋の方々が多いそうです。
シニア脳筋の方々、我流を本流と勘違いしないようにしましょう。そして、意図的に他人へ接触・引張りをするのは止めましょう。
我流と本流、フォーマルとアンチ
着物警察のように我流を本流と勘違いする発想は自分のなかに本物やフォーマルという妄想や幻想をもっています。
着物警察は本物妄想やフォーマル幻想、ニュー・キモノを指向してきた方々はアンチ・フォーマル。私からすると同じ穴の狢(むじな)。
服飾史家の大丸弘も諦めたように、このようなジレンマを突破する着物は今後も出てきません。すべて20世紀に出尽くしたからです。
だからといってニュー・キモノがダメだといっているわけじゃなく、21世紀は選択肢の時代だから選ぶことはできるということです。
突き抜けた新しさは無理でも、楽しい着物ライフをすごす選択肢を増やすため、ニュー・キモノの歴史を簡単にみていきましょう。
ニュー・キモノの歴史:断続的な人気
言葉からみてニュー・キモノは戦後のものです。
大塚末子が1950年代に発表した着物類を端緒にします。作品はこちら(学校法人大塚学院)。
この着物は、袖口を絞った上衣にモンペの下衣が組み合わされ、プリント柄が採り入れられていました。
この頃のニュー・キモノの発案者たちは新しい着物を考案しましたが、目的は着物を普段着に戻す着物ライフにありました。
その後、着物にネックレスやイヤリングなどのアクセサリーを付ける着方が増えました。
バブル経済の段階になった1980年代の中頃から、近代(明治・大正・昭和初期)を思わせる色や柄の着物が流行し、これらを最近ではニュー・キモノといいます。普段着から少し離れて、ちょっとしたお出かけに着る外出着のイメージです。
しかし、近代を一括できる時代になったわけですから、着物は異文化として理解され、伝統衣装とはいえなくなっています。
大塚末子が考えた普段着としての着物が現在からかけ離れたのが1980年代。
この時期以降に刊行されたファッション辞典類に「ニュー・キモノ」という用語が初めて登場しました。
ニュー・キモノの流行は大きく3つに大別できます。
- 高度成長期
- 1980年代
- 2010年代
これらの時代別にニュー・キモノを詳しく説明します。
高度成長期のニュー・キモノ
この段階は、大塚末子を発端にします。
大塚はアンチ・フォーマルかつ普段着としてニュー・キモノを作っていました。
大塚末子の著書をみると、
- 『新しいきもの双書〈第5〉部屋着・ねまき・下着』婦人画報社、1959年
- 『きもの実用学―晴着からふだん着まで―』婦人画報社、1967年
- 『新きもの作り方全書』文化出版局、1972年
など、部屋着・普段着や実用性を着装理念に、着物の自作(ハンドメイド)まで想定していたことがわかります。
3冊だけで判断して早急ですが、婦人画報社は1970年代からフォーマル化していったのでしょうか…。
ニュー・キモノの素材は絹に限らず、ウール(羊毛)や綿を使う場合もありました。
しかし、1970年代の石油危機頃から消費が鈍化し、洋服のなかでもスポーツ・ウェアが人気となり、街頭でも運動着が着用されるようになりました。
他方で着物業界は硬直化し、フォーマル一辺倒に傾きます。
戦前から始まっていた複雑な着物の規範化が高度成長期や1970年代をとおして強化され、成人式や結婚式のフォーマルウェアで暴利商売の土台が形成されいきました。
1980年代のニュー・キモノ
次にニュー・キモノが流行となったのは、新装大橋の大橋英士が火付け役となりました。
雑誌『anan』でニュー・キモノ特集が組まれました。
また、中森明菜が「ディザイア」でニュー・キモノを披露しました。中森明菜は「ディザイア」のシングル・レコードのジャケットに着物を着たため、この曲の場合はテレビ出演でも着物にこだわりました。
上の記事に述べましたが、この着物、かなり雑でダサい印象です。もちろん、歌唱力はエグいです。
1980年代のニュー・キモノは、ポリエステルで5万円くらいのものも販売され、かなり暴利が効いて勢いが良かったのですが、DCブランドをはじめ100ほどのブランドがひしめき合っていました。
そして、需要規模をはるかに超えた供給過多に陥り、数年で一気に消え去りました。
2010年代のニュー・キモノ
2010年代ともなると、1920年ころの大正ロマンが歴史化されて、1960年ころの高度成長期も歴史化されています。
このため、大正ロマンのキッチュで可愛い着物だけでなく、高度成長期のストイックで洋服化された着物も、外出着やレンタル衣装として着られるようになりました。
観光地化に成功した京都
2010年頃から日本では京都を中心に観光立国が目指されるようになりました。
2014年まで日本は韓国に観光業で負けていたのですが、京都観光地化に成功したことが一つの起因となり、韓国との順位がチェンジします(世界観光ランキング – Wikipedia)。
国内・海外からのリピーターが長期的に確保できるかはかなり怪しいです。
とりあえず京都観光地化の成功は、着物を着ると街中の喫茶店やレストランでおまけをして貰えるという「京都きものパスポート2016~2017」などの仕掛けが関わりました。このパスポートはコロナ禍で中止になりましたが。
個人的な実感では、この試みは海外からの旅行客にも大人気を呼んでいます。
20年ほど前まで閑古鳥しか鳴いていなかった鴨川デルタにまで、国内観光客も外国人観光客もやってきます(一部は着物を着て)。
私の教え子たちも授業の合間に散歩を楽しんでいます。随分と鴨川は変わりました。
観光地に外国人がレンタル衣装を使うことを想定して、2011年にズバリ「ニュー・キモノ」という本を七緒マガジンが出しました。
日本語話者からすれば外国人へ着物を説明するのに役立ち、外国語話者にはスタイルブックや背面の着付けに参考となるようです。
レンタル衣装の浴衣・着物ブーム
浴衣・着物ブームの一因に呉服屋が着物販売から着物レンタルに重点を移したことも考えられます。近年の着物レンタル市場は増加傾向にあります。
たとえば「きもの365」というレンタル・サービスは「一式セットで着物レンタル、お得に通販、着付け場所も探せる着物総合サイト」として、全国の呉服屋が集う着物レンタル・着物通販モールとなっています。
観光客の着物への人気爆発を全国的に対応していくには、このようなサービスも広域のレンタル・ショップをカバーしていく必要があります。
レンタル衣装がとりあつかう和装はいろいろ。留袖、色留袖、訪問着、振袖、卒業袴、色無地、小紋、産着、男着物などです。
貸し出すシーンは次のようなもの。結婚式、結納、七五三・お宮参り、成人式、入学式・卒業式、コンサート・お食事、パーティー。
『きもの文化と日本』の著者の一人、矢嶋孝敏(株式会社やまと代表取締役会長)は、1990年代から浴衣を積極的にカジュアル・ウェアとして販売するようになりました。
最近、どちらかといえば着物よりも浴衣に観光客の人気が集まっている点は1990年代に起因を求められそうです。
まとめ
和服の洋服化以後、20世紀をとおして着物は19世紀の姿を失いました。
ニュー・キモノは、フォーマルじゃないカジュアル路線を行くものです。
といっても、ニュー・キモノにも胸元の緩みはなく端折りの弛みもありません。裾を引くこともレンタル着物ではできませんし(自分や家族が買ってくれたものでも裾は引けませんが)、綿入もされません。
ニュー・キモノがどれほどカジュアルをめざそうとも、19世紀の着物・和服がもっていた自由な着方を許すものではありませんでした。
あくまでもフォーマルウェアの廉価版やアレンジ版という束縛から逃れることはできませんでした。
非生活的需要への依存という現象が、(花柳界と;岩本注)おなじような立場におかれた和服にもみられる。そのひとつは、日本人の心の故郷、日本の民族衣裳だから大事にしよう、という、いわば超越的観念化。第2は、むしろその非日常性の上に居直ったともいえる、アイデア遊びとしての、各種のニュー・キモノ。第3は、非日常的なものであるからこそ、人目を確実に惹く、という価値、いわば異装性の強調、などがそれである。大丸弘「現代和服の変貌Ⅱ―着装理念の構造と変容―」『国立民族学博物館研究報告』千里文化財団,第10巻1号、1985年7月、220頁
生活向け衣服として改良に失敗した着物・和服は、根本的な限界を孕んでいることを知ってください。平面の布を立体的な身体に巻きつけるのですから、限界や矛盾があります。
中森明菜は「ディザイア」でニュー・キモノを確かに着ましたが、それ以外の曲では洋服だったことを想起したいところです。




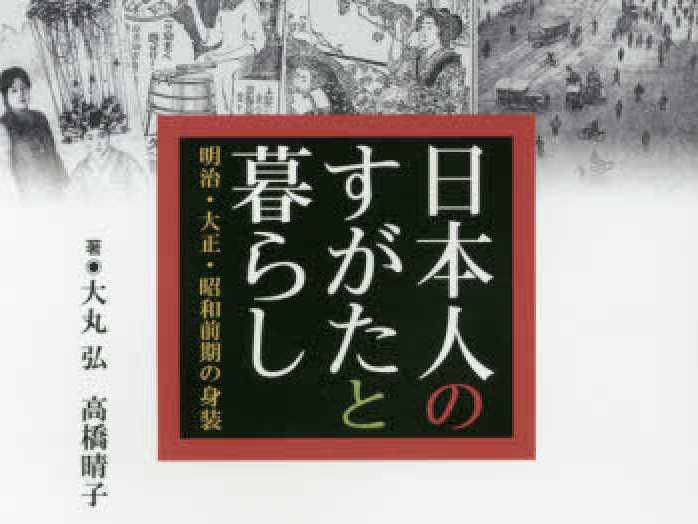
コメント